【PR】本記事は、ヨンデミー様から情報提供を受けて作成しています。
ヨンデミーは中学生でも使えますし、実際に中学3年生の利用者だっています。今回は中学生向けのヨンデミー活用方法や注意点など紹介します。
ヨンデミーは中学生の利用者もいる!

ヨンデミーは中学生の利用者もいます。
この点について、ヨンデミーの代表の方がインタビューで以下のように答えています。
ヨンデミーでは年齢や学年ではなく読書の成長段階をベースとしていることから、結果的には5歳前後から15歳くらいまでの幅広い年齢のお子様にご利用いただいています。
引用元:ベンチャー.jp
これ、すごく大事なポイントなんです。読書って、年齢で区切れるものじゃないんですよね。難しい本が好きな小学生もいれば、読みやすい物語から始めたい中学生もいます。
ヨンデミーは「今のその子」の読書レベルに合わせて本を選んでくれるから、中学生でも(あるいは高校生でも)ちゃんと楽しめるんです。
公式サイトには推奨年齢「6~12歳」とありますが、これはあくまで一般的な目安。お子さんが「読みたい本がわからない」と悩んでいるなら、年齢は気にせず試してみる価値は十分にあります。
ヨンデミーは中学生でも楽しめる本も紹介してくれる
「中学生の利用者がいても、ヨンデミーで紹介される本が子どもっぽかったら意味がないんじゃ…」という心配もあるでしょう。
ですが安心してください。ヨンデミーが提案する本は、いわゆる児童書だけではありません。
先月の読書の収穫は、この本かな。
— Sky@2027G (@SKYsince2014) April 4, 2024
登場人物4人の異なる視点で描かれ、時系列も前後する、わりと手の込んだ構成。
娘の好きな日常に近い青春モノというジャンルだったとはいえ、よく読めたと感心した。
巧みな構成もあって大人が読んでも楽しめる本でした!#ヨンデミー pic.twitter.com/zOcEbEFK0K
私が知る限りでも、映画やドラマ化された小説や、スポーツに打ち込む主人公の青春物語など、中学生のみならず大人でも楽しめる本がきちんとラインナップされています。
むしろ、この時期だからこそ出会ってほしい「ちょっと背伸びした一冊」を、絶妙なさじ加減で選んでくれるのが、ヨンデミーのすごいところだと私は感じています。
まずは30日間 無料で試せる!
★1日2時間のYouTubeが1日2冊の読書になる
中学生にヨンデミーがおすすめの理由
ヨンデミーは中学生でも使えるという点に加えて、私が「これは中学生にピッタリだ!」と感じる大きな理由があります。
それは、彼らが「娯楽にあふれている」世代だからです。

私が見てきた多くの中学生たちも、勉強にしろ娯楽にしろ、ヒマな時間というものがあまりなくて常に何かをやっていました。
「本を読みたい気持ちはあっても、本屋に行って面白い本を探すのがめんどくさい」
「そんなことをするくらいなら、手っ取り早くYouTubeでも見たり、ゲームがしたい」これが彼らの本音なんですよね。
ヨンデミーは、この「本を探す」という、意外と手間のかかるプロセスを、スマホ一つで解決してくれます。
まさに読書の時短です。忙しい日々のスキマ時間に、自分にぴったりの面白い本と出会える。この効率の良さが、今の時代の子どもたちに驚くほどフィットするんです。
また、多感な時期の彼らには「失敗したくない」という気持ちが強くあります。
「せっかく読んだのにつまらなかった」という経験は、大人が思う以上に彼らの心を折ってしまい、読書そのものから遠ざけてしまう原因にもなりかねません。
その点、AIとプロが選び抜いた本を提案してくれるヨンデミーは、ハズレが少ない。
最初の数冊で「面白い!」という成功体験を積める可能性が非常に高い。
この「小さな成功体験の積み重ね」こそが、読書を好きになる一番の近道だと、私は思っています。
中学生向けのヨンデミー活用法
ヨンデミーを「本を選ぶだけのサービス」にしてしまうのは、少しもったいないです。特に、心も体も大きく成長する中学生だからこそできる、効果的な活用法を2つほどご紹介させてください。
ヨンデミーを親子で楽しめるツールとして考える
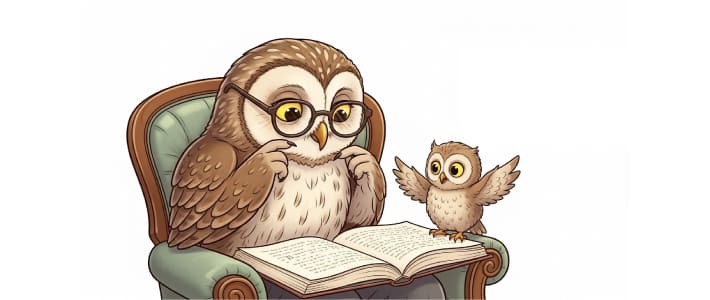
「最近、子どもが何を考えているかわからなくて…」。
中学生のお子さんを持つ親御さんから、よく聞く悩みです。親子の会話が急に減って、寂しさを感じることもありますよね。
そんな時こそ、ヨンデミーが架け橋になってくれます。
「今日はどんな本がおすすめされたの?」
「へぇ、面白そうだね。お母さん(お父さん)も読んでみようかな」
こんなふうに、ヨンデミーを親子の共通の話題にするんです。同じ本を読んで「あの場面、どう思った?」なんて感想を言い合えたら、最高のコミュニケーションだと思いませんか?
私も経験がありますが、本の話をきっかけに、学校のことや友達のことをポツリと話してくれることもありますよ。
SNSで読書アカウントを作って本の感想を発信する
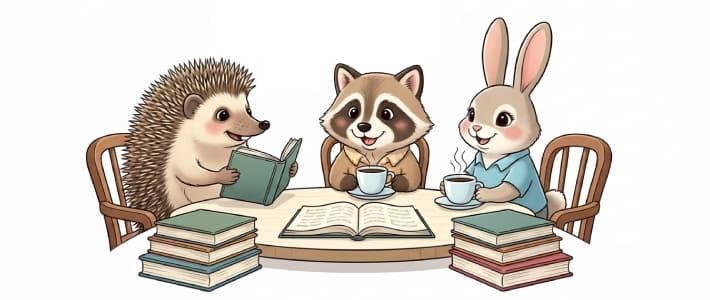
今の子どもたちは、自分の「好き」をネットで発信することに抵抗がありません。これを読書にも活かさない手はありません。
ヨンデミーで出会った本の感想を、SNSで発信してみるのです。「#読了」や「#読書記録」といったハッシュタグで検索すれば、たくさんの仲間が見つかります。
#読了 世界でいちばん透きとおった物語
— kusa@読書垢 (@kusa8085) September 3, 2025
凄い…凄すぎる…!!
衝撃と感動で3回くらい時間止まった
紙の本が好きな方は読むべき! pic.twitter.com/eYWRU6ROmA
いきなり感想文を書く必要なんてありません。『 〇〇(本のタイトル)。面白かった! #読書記録』この一言からで十分なんです。
まずはアウトプットする習慣をつけることが目的ですからね。心配な方は、最初は鍵アカウントで練習してみるのも良い方法です。
全員がそうではありませんが、私が知る限り、いわゆる「読書アカウント」の世界は、穏やかで優しい人たちが多いです。
※ネタバレになる発信は、読書の楽しみを奪うので絶対にしないようにしてください
お互いの感想を尊重し、好きな本について語り合う。自分の感想に「いいね!」がつく経験は、読書のモチベーションをさらに高めてくれるはずです。
中学生がヨンデミーを使う際のよくある質問
中学生がヨンデミーを使う際のよくある質問を紹介します。
ヨンデミーは本を届けてくれますか?
いいえ、ヨンデミーは現時点では本の配送や購入機能はありません。全国の図書館と連携しているので、アプリで貸し出し予約をして、お近くの図書館で借りるといった形式となります。
紹介された本が気に入らなかったらどうしたらいい?
そんな時に役立つのがヨンデミーの「YL相談所」という機能です。
もし「この本、なんだかちょっと違うな…」と感じたら、この相談所を使ってみてください。そうすると、AIがお子さんの読書レベルを丁寧に見直してくれて、新しくピッタリな本を改めて紹介してくれます。
まるで、行きつけの書店の店員さんに「この本は簡単すぎたみたいで。もう少し、うちの子に合いそうな本はありませんか?」と気軽に声をかけるような感覚です。
まずは30日間 無料で試せる!
★1日2時間のYouTubeが1日2冊の読書になる
私が親御さんに伝えたい、中学生がヨンデミーをする際の注意点
最後に、これまでたくさんの親子を見てきた私から、一つだけ大事なことをお伝えさせてください。
ヨンデミーは中学生でも使える素晴らしいサービスですが、あくまで「読書を好きになるキッカケを作るツール」だということを忘れないでほしいのです。
最終的なゴールは、ヨンデミーを卒業しても、自分の意志で本屋に足を運び、「次は何を読もうかな」とワクワクできる大人になること。私はそう考えています。
だから、もしお子さんが「もうヨンデミーはいいや」と言い出したら、無理に引き留めないであげてください。
それは、サービスに興味がなくなったのではなく、もしかしたら「自分で本を選んでみたい」という気持ちが芽生えたサインかもしれません。
その時は、ぜひ親御さんが昔読んで面白かった本をおすすめしてあげてください。
最初は漫画みたいで読みやすいライトノベルだっていいんです。どんな形であれ、本の世界と繋がっていることが何よりも大切なんですから。
読書は、お子さんの世界をどこまでも広げてくれる、一生の友人です。ヨンデミーを上手に活用して、その出会いの第一歩を、ぜひ親子で楽しんでみてください。


コメント