中学受験の国語に「速読」を持ち込むのは、やり方を間違えると逆効果になることもあるんです。ただ、読書が苦手子どもにとっては、ものすごい威力を発揮する「秘密兵器」になる可能性も秘めています。

中学受験で速読は効果があるのか?その真相について徹底解説していきます!
中学受験の国語では、ふつうの速読は効果があまりない
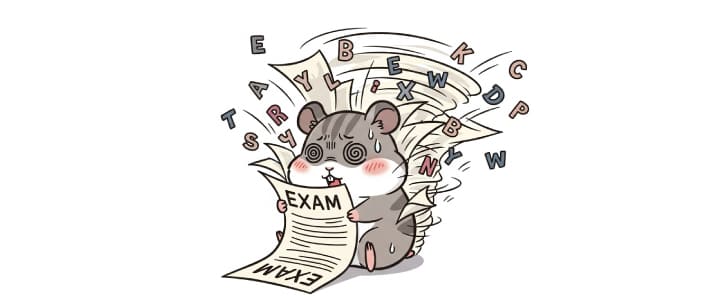
まず大前提として、とても大事なことをお伝えします。
一般的にイメージされる「普通よりも速く読んで、内容をザッとつかむ」みたいな速読は、中学受験の国語には残念ながら、あまり効果がないんです。
速読のスキルは中学受験の国語ではあまり役に立たない
「え、速く読めるなら中学受験の国語でも有利じゃないの?」と思いますよね。
その疑問に答えるために、まず「一般的な速読で身につくスキル」と、「中学受験の国語で本当に求められる力」をじっくり比べてみましょう。
速読で身につくスキル
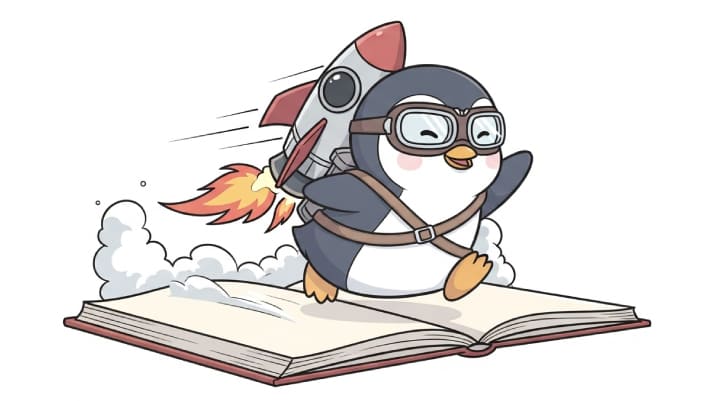
一般的に速読トレーニングなどで鍛えられるのは、主にこんなスキルです。
| 速読で身につくスキル | 概要 |
|---|---|
| 眼球運動の高速化 | 眼の筋肉をトレーニングして、視線をスムーズに速く動かす技術。 |
| 視野の拡大 | 一度にたくさんの文字や単語を視界におさめるトレーニング。 |
| キーワードの拾い読み | 文章の中から「重要そう」な言葉だけをピックアップして、全体像を推測する技術。 |
これらを一言でまとめるなら、「情報を効率よく取捨選択して、要点だけをつまみ食いするスキル」と言えるかもしれません。
山積みの資料から必要なデータだけを探したり、大量のニュースの中から関心のある記事を見つけたりするには、ものすごく便利な能力です。
【あわせて読みたい】
速読は本当に読めてる?読む速さと理解度の関係を解説
中学受験の国語で求められる能力

一方で、中学受験の国語が子どもたちに求めているのは、速読で身につく能力とはまるで違う、もっと繊細で深い能力なんです。
| 求められる能力 | 概要 |
|---|---|
| 登場人物の心情への共感力 | 「なぜ主人公は、ここで黙って空を見上げたのだろう?」といった、言葉に書かれていない心の機微を、前後の言動や情景描写から想像する力。 |
| 論理の迷路をたどる力 | 「しかし」「つまり」「なぜなら」といった接続詞を道しるべに、筆者がどんな理屈で主張を組み立てているのかを、一歩一歩正確に追いかける力。 |
| 根拠を探し出す探偵力 | 「傍線部にある『このこと』とは具体的に何を指しますか?」という問いに対し、本文中から「これだ!」という答えの根拠を、一字一句おろそかにせず探し出す力。 |
参考資料
成城学園中学校 入学試験問題 国語 2025年度
早稲田中学校 入学試験問題 国語 2025年度
速読が「つまみ食い」のスキルだとしたら、中学受験の国語の読解は「素材の味からシェフの隠し味までじっくり味わう」スキルです。
このように、速読と中学受験の国語では、求められる姿勢も技術も、正反対と言ってもいいくらいなんです。だから、普通の速読をいくら練習しても、なかなか国語のテストの点数には結びつかない、というわけです。
中学受験の国語に効果がある速読

「じゃあ、やっぱり速読なんて時間の無駄じゃないか!」そう結論づけるのは、まだ早いです。 ここからが、今回の話のいちばん大事なところです。
もし、あなたのお子さんが「読書が苦手」「本を読むのが遅くて嫌い」「活字を見るだけでウンザリする」という状態なら、話は180度変わります。その子にとって、速読が中学受験の国語を攻略するための「特効薬」であり「起爆剤」になることがあるんです。
速読で読書が苦手な子から、読書が好きな子へ
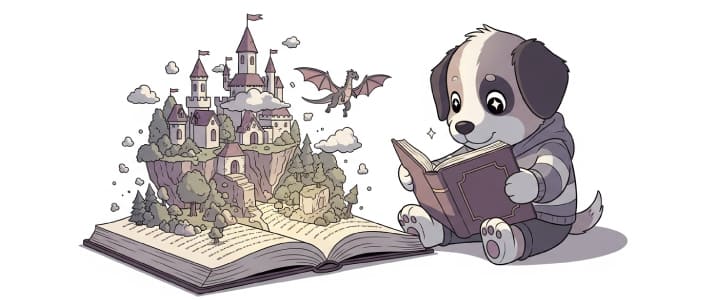
本を読むのが遅い子にとって、「読書」は楽しいどころか、ただの苦行でしかありません。
でも、もし、速読トレーニングを遊び感覚で取り入れて、「あれ?僕(私)、文字を目で追うの、意外と速いかも!」「なんだ、ゲームみたいで面白いじゃん!」と感じてくれたら、どうでしょう?
子どもを縛りつけていた「活字への見えないバリア」が、ガラガラと音を立てて崩れていくはずです。これが、私たちが目指す最初の、そして最も重要なゴールです。
活字アレルギーという名の呪いが解けると、子どもの世界は一変します。
「本って、もっと速く読めるものなんだ」と気づけば、「じゃあ、この本なら読めるかも」と、自分から興味のある本に手を伸ばす日が来るかもしれません。
こうして本を読む習慣が芽生えれば、しめたもの。
文章にたくさん触れることで、自然と内容をじっくり読む「精読」の力も少しずつ育っていきます。結果として、国語の成績が伸びていく。
こういう「最高の好循環」を意図的に作り出すこと、それが「中学受験の国語に効果がある速読」なんです。
【あわせて読みたい】
速読は小学生の習い事におすすめ?注意点なども解説
速読の目的を忘れないようにしよう!

ここで一つ、保護者の方に絶対守ってほしい約束があります。
それは、目的を見失わないことです。
もし親御さんが「速読トレーニングで、中学受験のために国語の偏差値を上げるぞ!」と肩に力を入れてしまうと、そのプレッシャーはお子さんに伝わり、かえって活字嫌いを加速させてしまいます。
おまじないのように、何度も心の中で繰り返してください。
「この速読の目的は、○○ちゃんの成績を上げることじゃない。ただ、『文字を読むのって楽しいかも』と思ってもらうこと。それだけ!」って。
この優しい眼差しがあれば、お子さんは安心して、そして楽しみながら活字の世界に足を踏み入れることができるはずです。
【あわせて読みたい】
速読を小学生で習うデメリット一覧
読書が苦手な子でも楽しめる速読トレーニングを探す

じゃあ具体的に何をすればいいか、おすすめの方法を2つのポイントでご紹介しますね
ゲーム性の高い速読トレーニングにする

難しい説明文や物語文は、今は必要ありません。
スマホアプリやゲーム機にあるような、上から落ちてくる単語をキャッチしたり、画面上を高速で動く文字を追いかけたり、時間内に特定の言葉を探したりするような、スコアやタイムが出るものがベストです。
「やった、今日の新記録だ!」という単純な達成感が、子どもの心をグッと掴みます。
「小さなできた!」を全力で褒める

「すごい!1分でこんなにたくさんの文字を目で追えたね!」「昨日より速くなってるじゃん、集中してたね!」と、どんな小さな成長でも見逃さず、思いっきり褒めてあげてください。
子どもにとって、親から褒められることは何よりのガソリンです。この「できた!」という成功体験の積み重ねが、苦手意識という大きな壁を溶かしていきます。
速読で中学受験の国語の点数を上げるための具体策
「遊びの速読」で活字へのアレルギー反応が薄れてきたら、いよいよ中学受験の国語の点数に直結させるための「橋渡し」のステップに進みましょう。ここでも焦りは禁物。「急がば回れ」の精神で、じっくりいきましょう。
STEP1. 興味のある短い本で「速読ごっこ」
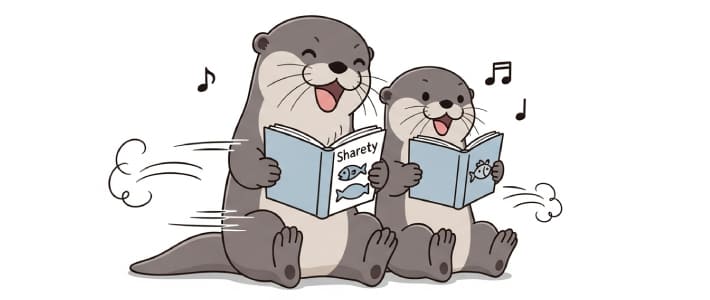
まずは、お子さんが大好きなアニメのノベライズ本、ワクワクするような恐竜や宇宙の図鑑、1話5分で読めるようなショートショート集など、お子さんが「これなら読みたい!」と思う本を用意します。
そして、「よーい、ドン!でどっちが速くこのページを読めるか競争しよう!」という感じで、「速読ごっこ」をしてみましょう。ストップウォッチでタイムを計るのも盛り上がりますよ。
この段階では、内容について細かく問い詰めるのはNGです。
「どうだった?」「どこが一番面白かった?」と、楽しさを共有するような軽い声かけで十分。「読書=楽しい時間」というイメージを定着させることが最優先です。
STEP2. 声に出して読んでもらう
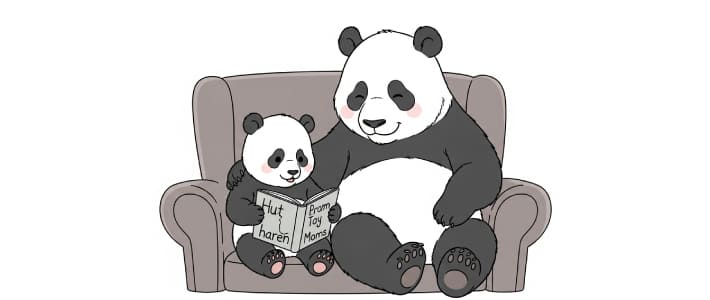
「〇〇ちゃん、すごく速く読めるようになったから、今度はその面白いところ、ママ(パパ)にも読んで聞かせてくれない?」と、自然な流れで音読に誘ってみてください。
実はこの音読こそ、速読とは真逆のようでいて、最高の「精読トレーニング」への入り口なんです。
声に出して読むことで、一語一語を意識せざるを得なくなり、「飛ばし読み」や「分かったつもり」を防ぐことができます。ここが、速読から精読への重要な転換点になります。
「精読」とは
細かい所まで、丁寧に読むこと
STEP3. 内容について話す
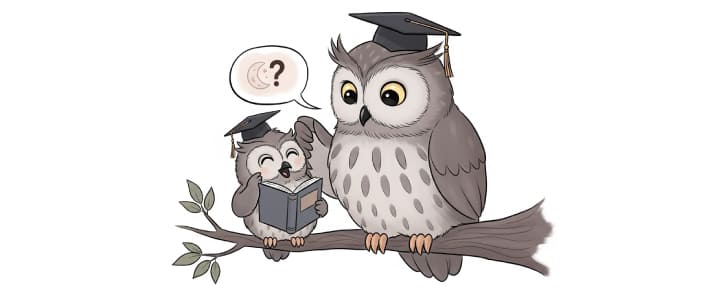
お子さんが音読してくれている横で、「へぇ、なるほどね」「この主人公、優しいなぁ」「え、ここでそんなこと言うの!? なんでだろう?」なんて、聞いている側も本気で楽しんで、相づちを打ってあげてください。
テストのように「はい、この時の気持ちは?」と質問するのではなく、
「親子で一緒にお話を楽しみ、謎を解き明かす仲間になる」という雰囲気を作ることが何よりも大切です。
このリラックスした対話の中で、「なんでだろう?」「どうしてこうなったんだろう?」とお子さんが自ら考え始める瞬間が訪れます。この「思考の芽生え」こそが、本物の読解力そのものです。
まとめ
読書が苦手な子にとって、速読は「きっかけ」。本当の勝負は、その扉を開けた後から始まります。
遊び感覚でできる速読トレーニングは、これまで分厚い壁に閉ざされていた国語という世界への扉を開けてくれるキラキラ光る「魔法の鍵」になり得ます。
でも、鍵で扉を開けただけでは、その部屋の中にある素晴らしい宝物(=文章の本当の面白さや、作者が込めた深いメッセージ)は見つけられません。
その未知の部屋を探検し、宝物を探し出す冒険こそが「精読」であり、中学受験の国語で本当に求められる力です。
どうか、「速読は、あくまで本格的な冒険を始めるための『準備運動』なんだ」と考えて、焦らず、お子さんのペースに寄りそうガイドになってあげてください。
その先にはきっと、お子さんが自信に満ちた顔で国語の問題に取り組む、輝かしい未来が待っています。応援しています!


コメント